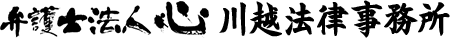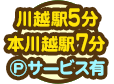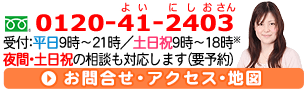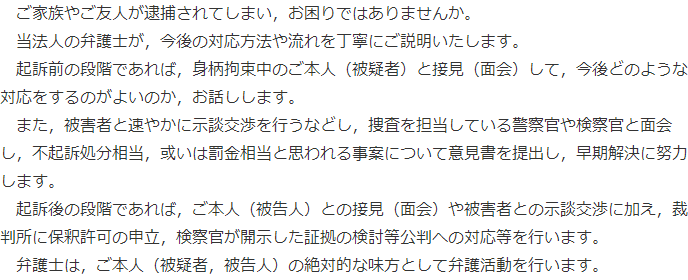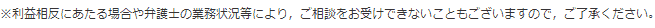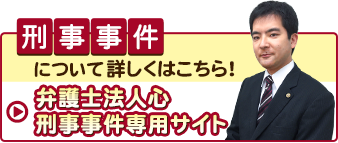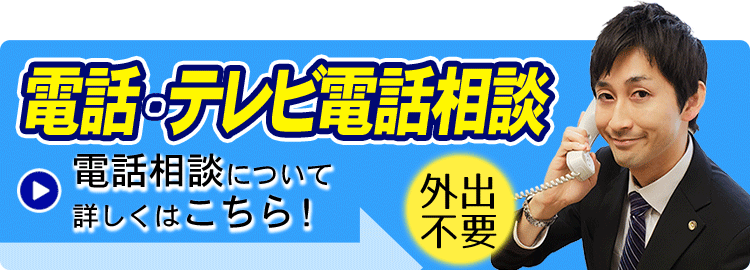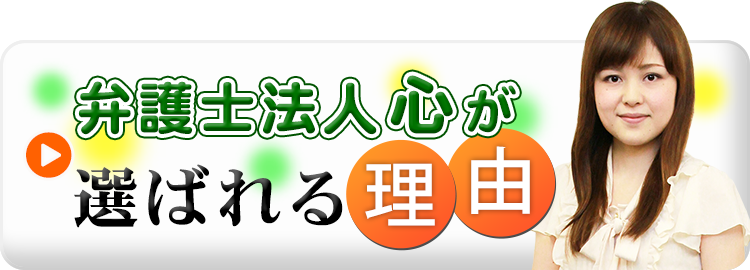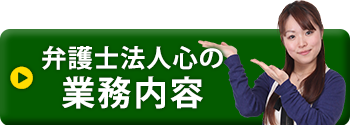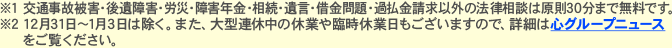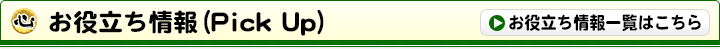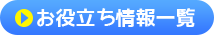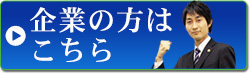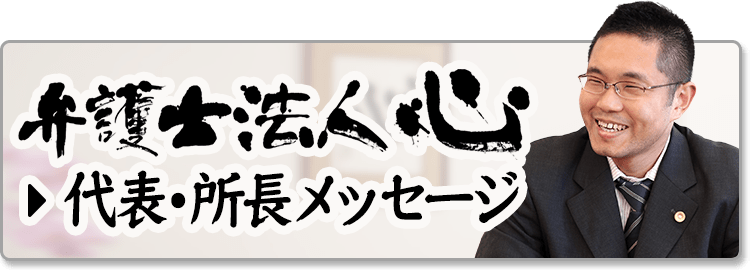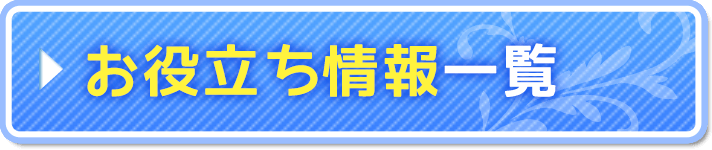刑事事件
刑事事件の弁護活動の流れ
1 起訴前と起訴後

刑事事件の弁護活動は、大きく分けて起訴前と起訴後で大きく分かれます。
以下、起訴前と起訴後に分けて説明します。
基本的には被疑者・被告人が犯罪を全部または一部認めている(自白している)前提で流れを説明します。
2 起訴前(捜査段階)の弁護活動
起訴前(捜査段階)においては、起訴を回避するための弁護活動が重要となります。
また、起訴自体は回避できないとしても、略式起訴による罰金刑となった場合、正式裁判である公判請求を回避することが可能です。
そのような不起訴等のために重要な弁護活動としては、一般的に、被害者への謝罪と共に被害者に対する示談交渉を試みることがあります。
また、被害者が存在しない犯罪又は被害者どうしても示談に応じない場合には、贖罪寄付や被疑者の反省や更生を裏付ける事情等がある旨の意見書を検察官に送付することもあります。
上記の弁護活動の中でも、特に重要なことは被害者との示談となります。
不起訴となるためには、起訴される前に示談を行う必要があるので、警察に事情を聴かれる段階になったら、弁護士に相談するというのがよいかと思います。
なお、起訴前に逮捕・勾留で身体拘束をされている場合、身柄を解放するため、具体的には、逮捕段階であれば勾留の阻止、勾留されてしまった場合には勾留の準抗告や取消しを求めたり、勾留延長の阻止をするため、上記の示談等の弁護活動をすることになります。
3 起訴後の弁護活動
起訴後については、基本的には裁判の準備になります。
検察側から出てくる証拠について間違いがないか、裁判官に誤った判断をさせるような証拠がないかを確認します。
実際の裁判では、もちろん証拠について意見を述べたり、尋問や被告人質問等被告人に有利になるよう活動します。
なお、起訴後においても身柄拘束されている場合(日本の刑事訴訟法では、被疑者段階で勾留されたまま起訴されると、そのまま勾留が継続してしまいます。)、保釈を求める等の活動をします。
4 裁判後について
判決が出た後、被告人と話し合い、刑が重い等の理由があれば控訴をすることになります。